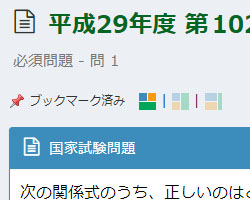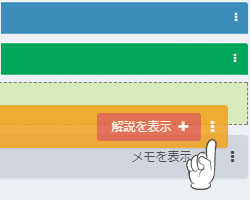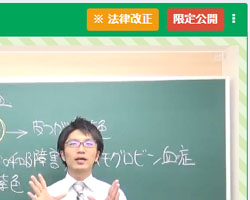配置を変更する
以下の配置に変更しますか?

- 変更した配置情報は保存され、別の過去問を見る際も適用されます!
- 配置の変更・保存は、パソコンで閲覧+解説動画がある過去問のみに適用されます。
- また一時的ですが、各パネルのヘッダー部分をマウスで掴んで動かすことも可能です。過去問を見やすい、学習しやすい好きな配置に変えてみよう!
※ ゲスト閲覧の方は、一時的に配置は変更されますが、保存はしていません。
※ 配置を保存して変更する をクリックすると画面は再読み込みされます。再生中の動画は引き続き、再生途中から再生が始まります。
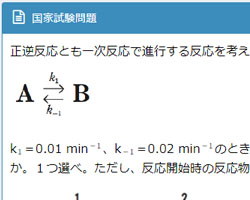
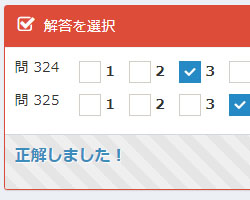
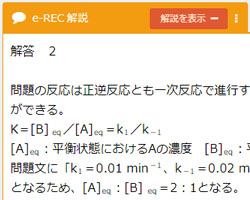
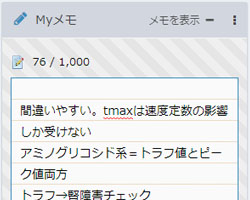
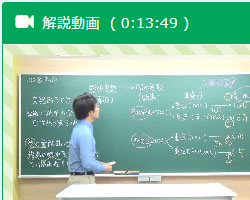

 |
|  |
|  |
|  をクリックして好きな配置に変更することが可能です。変更した配置は記憶でき、他の解説画面で
をクリックして好きな配置に変更することが可能です。変更した配置は記憶でき、他の解説画面で