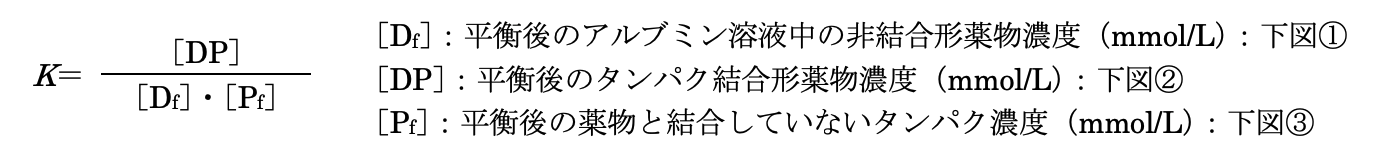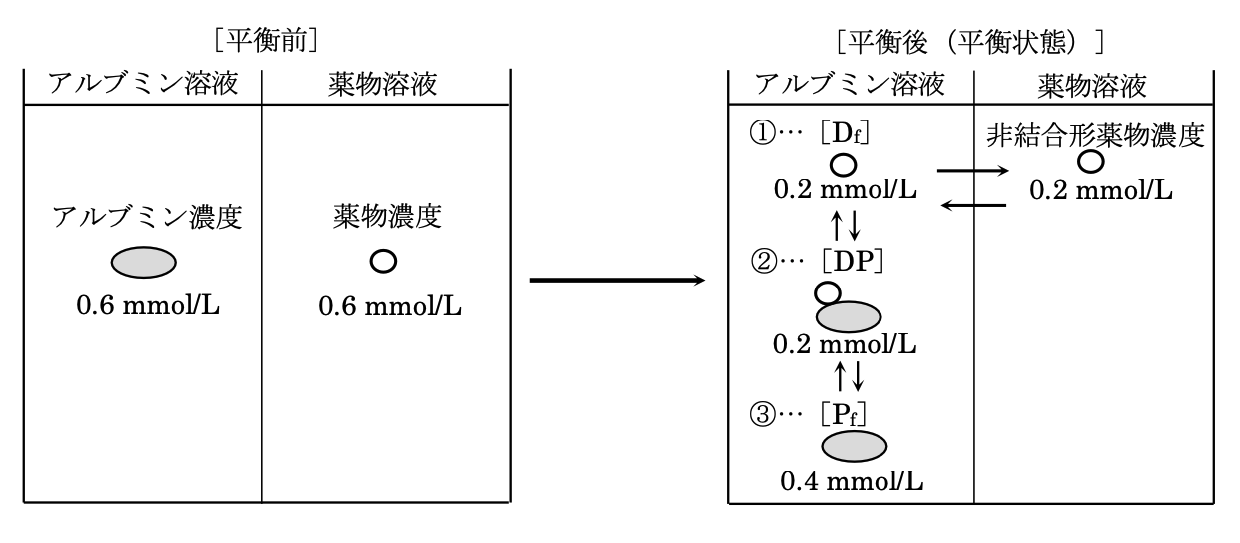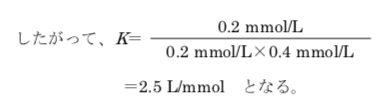薬剤師国家試験 平成31年度 第104回 - 一般 理論問題 - 問 165
ある薬物のアルブミンに対する結合定数を、平衡透析法を用いて測定した。半透膜で隔てた2つの透析セルの一方に0.6 mmol/Lのアルブミン溶液を加え、他方には0.6 mmol/Lの薬物溶液を同容積加えた。平衡状態に達したとき、アルブミン溶液中の薬物濃度は0.4 mmol/L、他方の薬物濃度は0.2 mmol/Lであった。薬物の結合定数K(L/mmol)に最も近い値はどれか。1つ選べ。ただし、アルブミン1分子当たりの薬物の結合部位数を1とし、薬物及びアルブミンは容器や膜に吸着しないものとする。
1 2.5
2 3.3
3 5.0
4 6.6
5 10
 REC講師による詳細解説! 解説を表示
REC講師による詳細解説! 解説を表示
-
 解説動画1 ( 11:22 )
解説動画1 ( 11:22 )
- ※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です
|
ビデオコントロール | |
|
|
| 再生速度 |
- この過去問解説ページの評価をお願いします!
-
- わかりにくい
- とてもわかりやすかった